ブログ
相続した家の売却にかかる税金とは?堤信之税理士事務所が解説
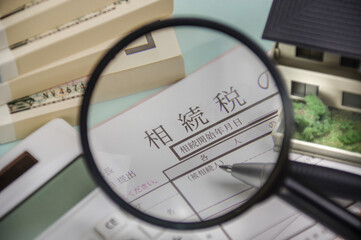
相続した家を売却すると、思いがけない税金が発生することをご存じでしょうか。東京都武蔵野市のような都市部では不動産価値が高く、税金の負担も大きくなりがちです。特に相続税と譲渡所得税はまったく別物であり、混同すると大きなミスにつながる恐れがあります。
相続した家の売却にかかる税金というテーマは、財産を引き継いだご家族にとって非常に重要なテーマです。相続税の納付が終わったと思った矢先に、不動産を売却したことでまた新たな税金が発生し、困惑するケースは少なくありません。税金の仕組みを正しく理解し、節税対策を講じることが、ご家族の資産を守る第一歩となります。
堤信之税理士事務所(東京都武蔵野市)は、これまで数多くの相続に関するご相談をお受けし、的確な節税対策をご提案してまいりました。本記事では、相続した家の売却にかかる税金の基本から節税のポイント、トラブルを避けるための対策、そして当事務所が提供するサポート内容まで、わかりやすく丁寧に解説いたします。
相続した家を売却する前にぜひ一度、この記事をお読みいただき、「じゃあ堤信之税理士事務所に相談してみようかな」と思っていただければ幸いです。
目次
相続と不動産売却の関係

相続不動産を売却すると税金がかかる理由
相続した家を売却すると、譲渡所得税という新たな税金が発生する可能性があります。この税金は、被相続人から引き継いだ不動産を売却することにより得た「譲渡所得」に対して課されるものです。
相続税とは異なり、譲渡所得税は「売却による利益」が発生したときに課税されます。売却価格から取得費(購入時の金額)や譲渡費用を差し引いた利益が課税対象となるため、地価の高い東京都武蔵野市では特に注意が必要です。
相続した家をすぐに売る場合の注意点
相続直後に家を売却する場合でも、税務処理は必須です。「売ってすぐだから税金がかからない」と思い込んでいる方もいますが、これは大きな誤解です。
相続開始後、遺産分割が済んでいなくても、売却によって利益が出れば譲渡所得税は発生します。また、分割協議中の不動産を売却するには、相続人全員の合意が必要です。これを怠ると、売却自体が無効となるケースもあります。
住んでいない家を売却する場合の税務リスク
自分自身が住んでいない相続不動産は、「居住用財産の特例」が使えない可能性があります。3,000万円特別控除などの特例を使えるかどうかは、被相続人がその不動産を居住用としていたか、相続人が相続後に実際に居住したかによって変わります。
適用要件を満たさなかった場合、税額は大きく跳ね上がる可能性があるため、事前の確認が不可欠です。特例の適用に関する要件は細かく定められており、税務署や専門家の判断が必要となります。
複数人での相続と売却の複雑さ
複数人で不動産を相続した場合は、売却の意思決定が一筋縄ではいきません。たとえば、兄弟姉妹などで不動産を共同相続した際に、1人でも売却に反対すると、その物件を売ることはできません。
また、売却後の利益配分についても明確な取り決めがなければ、のちのちトラブルに発展します。こうした事態を避けるためにも、早い段階で遺産分割協議を行い、必要であれば第三者の専門家を介入させるべきです。
専門家が必要な理由
相続と売却にまたがる税務処理は、極めて複雑かつ高度な判断を求められる分野です。誤った判断をしてしまうと、不要な税金を支払ったり、申告漏れによってペナルティを受けたりするリスクもあります。
堤信之税理士事務所(東京都武蔵野市)では、相続と不動産売却に関する税務を一括して対応しております。相続した家の売却にかかる税金に精通した税理士が、安心して任せられるサポートをご提供いたします。
相続した家の売却で発生する税金の種類

譲渡所得税の基本と計算方法
相続で取得した家を売却すると、「譲渡所得税」がかかる可能性があります。この税金は、売却によって得た利益に対して課税されるもので、相続税とは異なる扱いになります。
譲渡所得は、以下のような式で計算されます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
相続の場合、被相続人がかつて家を購入した際の取得費を引き継ぐことになりますが、古い物件ではその取得費が不明なケースも少なくありません。取得費が不明な場合は、売却額の5%を概算取得費とすることになり、税額が高くなりやすい点に注意が必要です。
このようなケースでは、堤信之税理士事務所(東京都武蔵野市)のように相続と不動産売却の双方に詳しい専門家へご相談いただくことで、税額の軽減を図ることができます。
取得費加算の特例とは
「取得費加算の特例」は、相続税を支払った人が一定期間内に家を売却した場合に利用できる制度です。相続税のうち、その不動産に対応する税額分を取得費に加算できるため、譲渡所得を圧縮することが可能となります。
たとえば、相続税として500万円を支払ったうち、家に対応する分が300万円と認められれば、その300万円を取得費に加算できます。結果として譲渡所得が少なくなり、課税額が下がります。
この特例を適用するには、相続開始から3年10か月以内に売却することが条件です。期限を過ぎると利用できなくなるため、早めに税理士へご相談されることをおすすめします。
3,000万円特別控除の活用条件
「3,000万円特別控除」は、マイホームを売却した場合に利用できる代表的な節税制度です。ただし、相続した家についてもこの控除が使えるかはケースバイケースであり、安易に適用を期待するのは危険です。
この控除が使える条件には、被相続人が亡くなる直前まで住んでいたことや、相続人が一定期間内に売却を行うことなどが含まれます。武蔵野市のような住宅密集地では、空き家のままにせず早期の売却を行うことで控除の可能性が広がります。
堤信之税理士事務所では、こうした細かい条件を1つずつ検討し、適切に制度を活用できるようサポートを行っています。
登録免許税・印紙税などのその他費用
相続で取得した家を売却する際には、譲渡所得税以外にも多くの費用が発生します。代表的なものに「登録免許税」や「印紙税」があります。
登録免許税は、不動産の名義を変更する際に課される税金です。相続による所有権移転登記でも一定の税額が発生します。また、家の売買契約書には印紙税が必要となり、売却価格によって税額が変動します。
これらの税金は少額ではありますが、積み重なると数十万円に達することもあります。そのため、事前に必要な経費を見積もることが肝心です。
具体的な税額のシミュレーション
相続した家を売却した場合に、どれくらいの税金がかかるのかを事前に把握することが重要です。堤信之税理士事務所では、お客様の不動産価値・取得費・相続税額などをもとに、具体的な税額シミュレーションを実施しています。
たとえば、相続により取得した家を5,000万円で売却し、取得費が不明だった場合、譲渡所得が4,750万円(取得費は250万円)と仮定されます。この場合、長期譲渡所得として約20%の税率がかかり、950万円もの税金が課される可能性があります。
しかし、取得費加算の特例や3,000万円控除を適用できれば、大幅な節税が可能になります。こうした計算は専門知識が必要なため、早めの相談が節税の第一歩です。
税金を軽減するための対策と準備

相続時点から始める節税対策
家を相続した時点から節税の準備は始まっています。相続後に不動産を売却することを見据えるのであれば、どの制度が使えるのか、どのタイミングで売却すべきかを明確にしておく必要があります。
例えば、取得費加算の特例を活用するには、相続開始から3年10カ月以内の売却が条件です。また、家屋の解体や修繕、登記の時期にも注意を払う必要があります。これらを把握せずに行動してしまうと、せっかくの節税機会を逃すことにもなりかねません。
東京都武蔵野市にある堤信之税理士事務所では、相続と売却の両面を見越した長期的な視点からの税務アドバイスをご提供しています。
家の評価額を適正に見直す
相続した家の評価額が高く見積もられていると、税金負担が必要以上に重くなる可能性があります。相続税の申告時や譲渡所得の計算時には、土地や建物の「適正な時価評価」が非常に重要です。
評価の方法には、路線価方式や倍率方式、そして実勢価格に基づく方法などがありますが、どれを採用すべきかの判断には専門知識が求められます。不動産鑑定士と連携した評価見直しを行うことで、税額が数百万円単位で変わることもあります。
堤信之税理士事務所では、相続税の還付実績も豊富で、評価額の見直しによる節税・還付支援にも力を入れています。
売却のタイミングを見極める
売却のタイミングを間違えると、節税どころか税負担が増えてしまう可能性があります。たとえば、控除や特例が使える期間を逃してしまうと、何百万円もの損失になることもあります。
また、不動産市場の動きも見逃せません。東京都武蔵野市のように需要の高いエリアでは、時期によって売却価格が数百万円単位で変動することがあります。節税と利益確保の両立を目指すなら、税金と市場の両方を意識した売却計画が必要です。
堤信之税理士事務所では、不動産会社との連携によるタイミング診断や資産活用のご提案も可能です。
節税制度の組み合わせ活用
税金対策は、ひとつの制度を使うだけでは不十分です。複数の制度を「組み合わせて活用する」ことで、最大限の節税効果を得ることが可能です。
たとえば、取得費加算の特例と3,000万円特別控除は併用可能です。これにより、譲渡所得を限りなくゼロに近づけることも可能です。しかし、要件が複雑なため、制度の相互関係を正しく理解しておく必要があります。
堤信之税理士事務所では、お客様の状況に応じた最適な制度の組み合わせプランをご提案し、申告までフルサポートいたします。
税務署への申告で気をつけたいこと
税金の申告は、単に書類を提出するだけではありません。記載の方法や添付資料の整合性が取れていないと、税務署からの問い合わせや調査が入ることもあります。
特に相続後の不動産売却では、相続税申告と譲渡所得申告の整合性が重要です。前後の申告内容が矛盾していると、税務署から修正申告を求められる可能性があります。
堤信之税理士事務所では、税務署対応を含めたトータルサポートを行い、申告ミスやトラブルを未然に防ぎます。安心して税務処理を任せられる体制を整えています。
トラブルを避けるための事前対策

遺産分割協議書の整備と合意形成
相続した家を売却するには、相続人全員の同意が必要です。そのためには、まず遺産分割協議書をきちんと整備しておくことが大前提となります。
特に複数の相続人がいる場合、「家を誰が相続するのか」「売却する場合の取り分をどうするのか」といった点を事前に合意しておくことで、後々のトラブルを回避できます。合意がないまま売却しようとすれば、登記もできず、買い手もつかない事態に陥ります。
堤信之税理士事務所では、弁護士や司法書士とも連携し、合意形成のプロセスから書面の作成、税務まで一貫してサポートいたします。適切な準備を行うことで、家の売却がスムーズに進む環境を整えます。
家の名義変更と登記のポイント
相続によって家を取得した場合、名義変更(相続登記)を行う必要があります。これを行わないまま売却を進めることはできません。売買契約を結ぶにも、登記簿上の名義人である必要があるからです。
この手続きは原則として義務ではなかった時代もありましたが、2024年4月以降は相続登記が義務化されました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
名義変更の際には登録免許税や必要書類の整備も求められます。堤信之税理士事務所では、こうした実務を含めた全体の流れを把握したうえで、必要なアクションをアドバイスいたします。
相続人間の意見の食い違い対策
家という不動産は、金銭のように簡単に分割できないため、相続人間で意見が対立しやすい資産のひとつです。「住み続けたい人」と「売却して現金化したい人」がぶつかる場面は珍しくありません。
このような状況に陥った場合、税理士が間に入り、経済的観点からの選択肢を提示することで、感情的な対立を緩和できる場合があります。特に東京都武蔵野市のような人気エリアでは、物件の売却価格も高額になることから、慎重な判断が求められます。
堤信之税理士事務所では、家を売却すべきか、賃貸にすべきかといった選択肢も含めてシミュレーションを提示し、ご家族全員にとって最善の解決策を見出す支援を行っています。
売却後の収益分配ルールの設定
家を売却したあとの売却代金をどのように分けるかは、事前に明確にしておかなければ、トラブルの火種となります。「不動産の名義が1人だが、実質的には全員の共有物だった」というケースでは、収益分配のルールを決めておかなければ不公平感が残ります。
相続時点でしっかりと分配の割合や手法を取り決め、書面に残しておくことが重要です。また、売却後に譲渡所得税が発生する場合は、誰が納税するのかも明記しておくと安心です。
堤信之税理士事務所では、家の売却前に収益分配と納税のルールを整えることで、後の揉めごとを防ぎ、ご家族全員の納得感を大切にしたサポートを行っています。
相続税と譲渡所得税の二重課税防止策
家の相続と売却において、もっとも誤解されやすいのが「税金の二重課税」です。相続時に相続税を支払ったにも関わらず、売却によって譲渡所得税も課されることに不満を感じる方も少なくありません。
しかし、これは制度上当然の仕組みである一方、取得費加算の特例や3,000万円控除などを活用すれば、大きく税負担を軽減することが可能です。これらの特例を適用せずに申告してしまうと、過大な税金を支払ってしまうことになります。
堤信之税理士事務所では、相続税と譲渡所得税を一体として考え、税金の過払いが起きないよう綿密に対策を講じています。正しい知識と経験が、結果として節税につながります。
堤信之税理士事務所にできること

相続税と売却時の税金を一括対応
相続にかかる税金と、不動産売却にかかる税金は別物ですが、相互に関連しています。多くの方がこれらを別々に処理しようとして混乱や損失を招いてしまいます。
堤信之税理士事務所では、相続税と譲渡所得税の両方を一括して対応できる体制を整えています。相続税申告の段階から将来的な不動産売却を見据えたアドバイスを行うことで、無駄のない節税とスムーズな資産移転を実現します。
特に東京都武蔵野市のような不動産価値の高い地域では、売却益も大きくなりがちです。事前に最適な税務設計を行うことで、最小限の税負担で最大の資産活用が可能になります。
財産評価の適正化による還付サポート
相続税の評価額が不適切だった場合、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。相続税の申告から5年10か月以内であれば、税務署に更正の請求を行い、還付を受けることができます。
とくに土地などの不動産は評価が複雑で、専門知識がないまま申告すると高額な税金を納めてしまうケースも多々あります。堤信之税理士事務所では、過去の評価を再検証し、適正な評価をもとに相続税還付の可能性を探ります。
実際に、土地評価の見直しによって数百万円以上の税金が戻ってきたケースもあります。これは相続した家を売却した方にとっても大きな助けとなります。
生前からの税務シミュレーション
相続は亡くなってからではなく、生前の段階で対策を始めることが重要です。家を誰に残すのか、売却するのか賃貸にするのか、どの制度が使えるのかを早期に整理しておくことで、円滑な相続と節税が可能になります。
堤信之税理士事務所では、生前贈与・家族信託・不動産評価見直しなど、多角的なシミュレーションを実施し、ご家族の将来設計に寄り添ったご提案を行っています。
特に東京都武蔵野市のような資産価値の高い地域では、遺産総額が思った以上に大きくなるケースが多く、税金対策の有無が大きな差となって現れます。
納税資金対策と資金繰りのご提案
家は相続できたが、税金を払う現金がない――そんなお悩みもよく寄せられます。特に現金以外の資産が多い方にとって、相続税や譲渡所得税の納税資金の確保は大きな問題です。
堤信之税理士事務所では、納税資金をどう確保するか、売却のタイミングをどう調整するか、借入や物納の選択肢はどうかなど、多角的な資金繰りのアドバイスを実施。
「相続税を払うために急いで売却した結果、安値で手放してしまった…」という事態を避けるためにも、税と資金の両面からサポートできる専門家が必要です。
ご家族の安心を守る伴走支援
相続や家の売却は、単なる手続きではなく、ご家族の大切な未来に関わる問題です。堤信之税理士事務所では、単に書類を整えるのではなく、ご家族の想いに寄り添った形でサポートを行います。
「どこから手をつければいいかわからない」「不安が多すぎて前に進めない」という方も安心してください。私たちは、最初の相談から相続税申告、売却、税金の納付、そしてその後の生活設計まで、長期的な視点でご支援します。
東京都武蔵野市に根ざし、多くのご紹介をいただいてきたのは、安心と信頼を大切にした対応を続けてきた結果です。
よくある質問Q&A

Q1:相続した家を売るのに税金はいくらくらいかかりますか?
相続した家を売却した場合の税金は、売却価格、取得費、譲渡費用、適用できる特例などによって大きく変動します。譲渡所得税は、利益に対して約20%(所得税15%+住民税5%)がかかるのが一般的です。ただし、取得費加算の特例や3,000万円の控除などを活用すれば、税負担を大きく軽減することが可能です。
Q2:取得費が不明な場合はどうすればいいですか?
被相続人が不動産を購入した際の資料(売買契約書など)がない場合、原則として売却価格の5%を概算取得費とするルールが適用されます。これは非常に不利になるため、過去の資料を探したり、専門家が再計算することで、正確な取得費を算出できるケースもあります。
Q3:相続した不動産の名義変更をしていなくても売却できますか?
できません。不動産の売却には、所有者としての名義が登記簿上に記載されている必要があります。相続登記を済ませていない場合は、まず名義変更の手続きを行ってからでないと、正式な売買契約を締結することはできません。
Q4:相続税の支払いと売却の税金、両方とも支払う必要がありますか?
はい、基本的には両方の税金が発生します。ただし、取得費加算の特例などにより、相続税の一部を売却時の取得費に加えることで、譲渡所得税を減らすことが可能です。この制度を上手く活用することが、税負担を抑えるカギになります。
Q5:家の売却時に使える控除制度にはどんなものがありますか?
代表的なものに「居住用財産の3,000万円特別控除」「取得費加算の特例」「長期譲渡所得の軽減税率」などがあります。どの控除が使えるかは個別の状況により異なるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
Q6:売却時に複数人の相続人がいる場合、どのように進めるべきですか?
まず遺産分割協議書を作成し、家の所有権を明確にします。売却するには全員の同意が必要であり、収益の配分方法も事前に決めておくことが重要です。堤信之税理士事務所では、相続人間の意見調整も含めたサポートを行っております。
Q7:相続税を払いすぎていた可能性があるのですが、取り戻すことはできますか?
はい、相続開始から5年10カ月以内であれば、更正の請求を行って相続税の還付を受けることが可能です。特に土地の評価額が過大だったケースでは、還付される可能性が高いため、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ

相続によって家を受け継いだあと、その家を売却することで新たな税金が発生することをご存じない方も多くいらっしゃいます。相続税と譲渡所得税は別の仕組みで、それぞれに対策が必要です。そのため、税金のことを後回しにして売却を急ぐと、必要以上の税負担や申告ミスに繋がる恐れがあります。
この記事では、以下のようなポイントをご紹介しました。
- 相続した家を売却することで発生する税金の仕組み
- 税額を軽減するために活用できる特例や控除制度
- 名義変更や遺産分割などの必要な手続きと注意点
- 相続人間のトラブルを防ぐための具体策
- 専門家による一括サポートの重要性
東京都武蔵野市に拠点を置く堤信之税理士事務所では、「相続」「家」「売却」「税金」に関するお悩みを一つひとつ丁寧に伺い、最適なアドバイスと実務支援をご提供しております。
私たちは、紹介で選ばれ続けてきた実績と、お客様の不安に寄り添う誠実な対応を大切に、相続の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。
もし、相続した家の売却をお考えであれば、税金のことで損をしないためにも、まずはお気軽に堤信之税理士事務所までご相談ください。税務と家族の未来に強い専門家が、全力でサポートさせていただきます。



